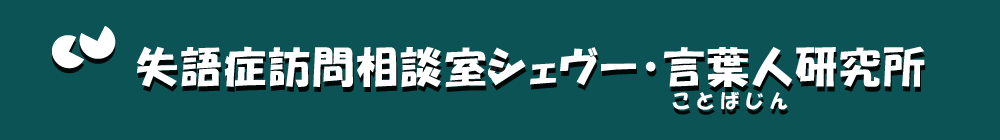
《ひと言様々》
 | |
| 言葉と人をめぐる、 |
|
【あ】 ●「全世界的に、近代の三百年間、多義的なもの、あいまいなものはだめだといわれてきた。それが、「あいまい」ではなく「多義的」なのだという積極的評価に転換しようという大きな動きが1920年代に英文学の中にあり、1960年代になって、「多義的」に価値を与える動きがたしかによみがえってきた。それを山口人類学はきちんととらえていたということになろう。こうして二十世紀に入り、シェイクスピアが「多義的」として新たな評価を受けることになる。かつてシェイクスピアは、「あいまい」と言われ、没後すぐピューリタンたちに痛めつけられた」(高山宏『近代文化史入門 超英文学講義』、講談社学術文庫、2007、p.36)。→cf.●「イギリス王立協会、言語観」 【い】 ●「先生、生きる可能性はありますか?」(ある失語症の女性が担当の言語聴覚士へ発した言葉。身体的にはすでに落ち着いていた時期なのに)。→cf.●「うちに帰っても心配」へ ●「人間の言説はどんなに分析的でも意味の最終的意味は分からない」(ジョージ・スタイナー〔工藤政司訳〕『真の存在real presences』、法政大学出版局、1989=1995、p.225)。 ●「人々があるものの意味に気づくのは、決まってそれが消滅しようとするときである」(柄谷行人『哲学の起源』岩波書店、2012、p.94)。 【う】 ●「うちに帰っても心配だし、…うちに帰ってもかえってやることなくて、帰って、あれかなあ…」(「生きる可能性がありますか」と言っていたある失語症の女性。その2か月後、担当の言語聴覚士へ発した言葉。現実的・具体的な悩みへ)。 ●「ごめんね。―『ううん』」(M,2003.11)。 ●「質問者ー両親がなく、特に養母との行動に問題のある子どもにたいしては、どう対処したらよいでしょう。この子は何でも壊し、いろんなところでウンコをします。ドルト―その子はまだ喪を行えない状態にあります。ウンコをもらすのは、母親の喪が行えなかったことを意味する行動です。ウンコは、子どもが小さかったときの、母親をそばに呼ぶ臭いを表わしています。自分のまわりにウンコを撒き散らすのは、ですから、彼=ママの臭いを撒き散らしていることなのです」(フラソワーズ・ドルト〔小川豊昭・山中哲夫訳〕『子どもの無意識』、青土社、p.143) 【え】 ●「何かを得るには、悲しいかな、何かを失わなくてはならない。何かを失うと何かをつかまされてしまう。それを拒否するなら、死ぬしかない」(nakan,2013.7.4)。 【お】 ●「音(おと)たちbruitsは、目立たず困難なものを求めるかのごとく、声をめざす身体が浸み込んだものとして、聞くべきものである。排泄物や音の効果bruitageには、声を求めるお喋りな身体が浸み込んでいるのである。要するに、よだれ、鼻汁、汗、糞などは、口唇的なものや性器的なものの失敗と対をなす全身に広がった肛門的享楽を示す排泄物として価値があるのではない。自閉症者がよだれと共にあらゆる廃棄物をあふれ出るままにしている時、彼は肛門でも肛門的な口でもない。自閉症者はもはやそうしたものに帰着しない。身体のあらゆる穴、皮膚すべてから流れ出て現われるものは、何よりも先ず音のするものle sonoreに関わる問題という隘路を経由する限りでしか認識できない。つまり、それは聞かれなければならないのである。口から流れ続けるよだれは、顎の脱臼や歯ぎしりと厳密に言えば同じものであり、それ自体厳密に言えば胸郭の振動と同じである。それは切れ目coupureを知らない音立てbruitementなのである。様々な形式の汚物、滲出物、表出はすべて、厳密に言えば、穴や切れ目を知らない身体の表面たち(皮膚、歯など)に作られた洞窟から響く音たちbruitsと同じものである」(SERGE HAJLBLUM, Hors la voix: Battements entre aphasie et autisme. 2006,p.123)。 ●「思い出すことはあらためて知ることにほかならない」(ジョージ・スタイナー〔工藤政司訳〕『真の存在real presences』、法政大学出版局、1989=1995、p.9)。 ●「おねえちゃん!おねえちゃん!」(98歳女性の言葉のエネルギー。世界を創造し、世界に呼びかける言葉である。2013.5.12)。 【か】 ●「始めに神が天地を創造された。地は混沌としていた。暗黒(やみ)が原始の海の表面にあり、神の霊風が大水の表面に吹きまくっていたが、神が、「光あれよ」と言われると、光が出来た。神は光を見てよしとされた。神は光と暗黒との混合を分け、神は光を昼と呼び、暗黒を夜と呼ばれた。こうして夕あり、また朝があった。以上が最初の一日である。・・・」(『旧約聖書 創世記』〔関根正雄訳〕、岩波文庫、1999、p.9。以上は「神はその創作の業を七日目に完了し、七日目にすべての創作の業を休まれた」とされる天地創造の第一日目の記述である。神が天地のすべてを創造するところから始まる。神は超越的なものとして、その誕生、出自は書かれておらず、神および神“以前”は問われていない。すべてが神から始まる。その神は独りで言葉を発し、光をつくり、その光を昼と名づけ、暗黒を夜と名づける。神はことばを話すが、それはものを創造し、ものを名づけるためであり、他の神々と会話するためのものではない)。 ●「イザナギノ尊とイザナミノ尊とは(二神は)、天と地との間に懸けられた天浮橋の上に立ち、互いに相談して言うには、『この下のほうに、どうして国のないことがあろう?』。こう言って、玉飾のしてある美しい天沼矛(あめのぬぼこ)を差し入れて、下の方を探ってみたところ、蒼海原を得ることができた。・・・」(『現代語訳 日本書紀』より「国生み」の箇所、河出文庫〔福永武彦訳〕、2005、p.22。『創世記』の記述と比べると大変対照的である。日本書紀で最初に言葉をめぐる記述が出てくるのは、この「この下のほうに、どうして国のないことがあろう?」と言う個所である。二神が相談し会話する場面がいきなり登場し、しかも神が名付けて事物を創造することはない。神の言葉は会話するためのものなのである。また、日本書紀では、天地は神が造ったのではなく、混沌から生じるのであり、その後に神が生まれるという神の出自も書かれている)。 ●「さて初めに宇宙に現われた三柱の天神は、この時、相談のうえ、イザナギノ命とイザナミノ命との二柱の神に、次のような言葉を与えた。『地上の有様を見るに、まだ脂(あぶら)のように漂っているばかりである。お前たちはかの国を、人の住めるように作り上げよ。』このように命令して、天沼矛(あまのぬぼこ)という玉飾を施した美しい矛を授けた。・・・」(『現代語訳 古事記』より「イザナギノ命とイザナミノ命」の箇所、河出文庫〔福永武彦訳〕、2003、p.28-29。『古事記』でも最初に言葉に関する記述が出てくる個所はイザナギ、イザナミの登場する場面である。『日本書紀』とは若干異なっていて、三柱の天神がイザナギ、イザナミの二神に命令するという形だが、やはり 神々の間で会話する場面である。) ●「書くこと、話すことは、有無を言わさずに受動的に『言葉を話す存在』とさせられた人間がその負債を返済しようとできる唯一の手段である」(nakan,2014.4.18)。 【き】 ●「人間が狂気であるのは必然的であるので、狂気でないことも、狂気を別の仕方で検討すれば、やはり狂気であろう」(パスカル『パンセ』414、1670〔中西之信 私訳〕。 白川静「狂気論」(『文字遊心』、平凡社、1996、p.13.所収)から発見)。 ●「少しだけ考えること、つまり少しだけ疑問をもつことは、知的で、「理性的」なことと見なされる。しかし、世界の存在を含むすべてに疑問をもつことは、狂気である。このことは、理性的に考えることには、すべて狂気が浸透していたことをあらためて気づかせる。同じように、自分の家の庭の中で芝刈り機を使うのであれば、当たり前の正常な家事だが、すべての道を芝刈り機で移動するならば、狂気である。とすれば、翻って、庭の芝刈りの中にも、一滴の狂気が含まれていることになる」(大澤真幸『生権力の思想』、ちくま新書、2013、p.236)。 ●「『聞く』とは大事なことを聞くことである。『話す』とは大事なことを話すことである」(nakan,2013.7.26.ジャーゴン失語症者がなぜ医療者の言うことをほとんど聞かないのか? 医療者が大事なことを話さないからである。重度失語症者がなぜ医療者にほとんど何も喋らないのか?医療者が大事なことを聞かないからである)。 ●「規則や規範があるのは、それ以前にすでに奔逸で過剰な戯れ、活動が存在しており、そのためある観点からはその戯れに規制をかけざるを得なくなったからである。言語に規則や規範があるのも同じである。失語症とは、言語を失ったのではなく、言語本来のそうした奔逸で過剰な戯れの現われである」(nakan,2013.8.5)。 【け】 ●「朝子には事実自分のあれほどの悲しみが、物語の一種であった、ということはつまり、一種の感情の怠惰であった、と省みられるふしもあった。こう考えると、すべての『在り得ないこと』は判然とする。あの事件の異様な偶然も、物語となれば判然とする。しかし彼女は二人の子と安枝の生きていた頃のあの生活まで、物語の中に塗り籠めてしまう勇気はなかった。今にしてみればあれこそ物語のように思われる幸福の喚起ほど、今の彼女にとって現実的なものはなかったからである」(三島由紀夫『真夏の死』(1952.8.15)、新潮文庫『真夏の死』(1970)、p.228)。 ●「イギリスでは、1662年、勅許をもらって王立協会が実質的に出発した。その5年後に『王立協会史』という決定的な本が出た。トマス・スプラットという初代の(名目的な)総裁が書いた本だが、「今後あらゆる言語と記号はシンプリシティーを旨とすべし」とうたう。単純にいくべしというのだ。これはアンビギュアスなものとは逆で、「サン」と聞いたら、百人のうち百人全員が「太陽」を思い浮かべるべきで、「息子」を思い浮かべてはならないという言語観である。・・・〔この〕 王立協会の表象革命〔が〕シェイクスピアを殺したのだ」(高山宏『近代文化史入門 超英文学講義』、講談社学術文庫、2007、p.50,55)。→cf.●「表象」 ●「言語というものは、あるがままの世界を人間が受け入れることを拒むための主要な道具立てなのである。こういう拒絶がなければ、そして、<反‐世界>を人間の心によって不断に作り出してゆくことがなければ―こういう作り出しは、反‐事実、および、希求法の文法形式と切り離すことはできない―、我々は現在という踏み車〔昔、獄舎で懲罰のために用いたもの〕を永久に廻し続けることになってしまうであろう」(ジョージ・スタイナー〔亀山健吉訳〕『バベルの後に・上』、法政大学出版局、1975,1992=1999、p.388)。 ●「『いろいろな言葉を並べてみれば分かるのであるが、言葉で問題になるのは、真実ではなく、また、十全な表現でもない。というのも、そうでないとすれば、これほど多くの言葉があるはずはないからである』(ニーチェ、『道徳とは関わりのない意味における真実と嘘について』より)。もっと単純に言ってしまえば、一方において、人間の言語の中の〈非‐真〉、すなわち、虚構の精神と、他方、人間の言語の多様性との間には、決定的で直結した相関性があるわけである」(ジョージ・スタイナー〔亀山健吉訳〕『バベルの後に』(上)、法政大学出版局、1975,1992=1999、p.414)。 【こ】 ●「近頃は、せいぜい三、四十人の集まりでも、発言者はマイクロフォンを使うことが多いようだ。聞いている人は、特に会議の場合など、どこか不特定の場所に設置されたスピーカーから響いてくる、方向性のない音の流れに身を浸しながら、語られている文章の内容を判断しては、ふむふむと賛成したり、なにを言ってるかと反撥したりして、そこではじめて話し手の顔をまじまじと見つめる、といった具合になる。みな、ことばの内容だけを取り出して判断材料にしようと身構えているだけで、話しかけている人そのもの、「わたし」という存在とはかかわろうとしていない。これが現代社会の風景だ。人が人に話しかけ人が人を聞く、ということからはほど遠いのではなかろうか。声とは人が人にじかにふれてゆく仕方そのもの、人と人との関わりの原点、であるのに」(竹内敏晴『声が生まれる 聴く力・話す力』、中公新書、2007,p.205)。 ●「・・・それら排泄物たち(よだれ、鼻汁など)は身体のある種の社会的受け入れ難さを納得するための根拠になったり、また別のことを示すとしても、私はそうした排泄物たちを、声である対象に関する本質的困難として、つまり対象‐声の特殊性、自在さとして擁護する。声は排泄物たちによって、不可能という様態によって意味され、対象として生じるにいたる。排泄物たちは声を目指しているのである。・・・自閉症とは声を対象の問題とする人間の様式であると言おう。自閉症とはまさに、人間を現に人間としているものの核心において、人間を問いに付すものである。人間の核心にあるのは声である」(SERGE HAJLBLUM, Hors la voix:Battements entre aphasie et autisme. 2006,p.121)。 ●「(気管カニューレがはずれ気管切開が閉じて、ようやく声が自分の意のままになるようになり、治療者に発した第一声)いい気持だよー、最高だよー、生きていく自信が出来たよ」(70代、男性、2013.7)。声という存在が人間にとり如何になくてはならないものか)。 ●「声は触覚である。ささやかれることの快。ささやくことの快。声を聞くことの快。声を出すことの快。響くことの快。肌に触れる快。何ものにも替え難い。今も響き続ける」(nakan,2013.8.10)。 ●「秋山のしたひが下に鳴く鳥の声だに聞かば何か嘆かむ(秋山の色づく下に鳴く鳥のように、せめて声だけでも聞けたらどうして嘆こう)」(『万葉集』巻第十、2239、『万葉集(二)』〔中西進訳〕、講談社文庫、8世紀後半=1980.秋の相聞歌の一つである。相聞とは、互いに相手の様子を尋ねること、消息を通わせ合うこと、互いにことばをかけ合い、歌い交わすことである。言葉でなくてよい、声さえ聞ければ・・・。声はやはり触覚である)。 ●「人間には“言葉になる”時がある。言葉になってようやく生きていける、という時がある」(nakan,2013.5.4)。 ●「ある言葉が失われるということは、言語がわたしたちのものではないということを意味している。わたしたちの内部の言語が後天的であるということは、それが棄てられることもありうるということだ。わたしたちがその遺棄のなすがままになりうるということは、言語活動全体が言語の果て〔舌の先=le bout de la langue〕へと曳いていくことがありうるということだ。ということは、わたしたちが自分の生まれた厩へと、ジャングルへと、前幼年期へと、あるいは死へと遡行するということもありうるということだ」(パスカル・キニャール〔高橋 啓訳〕、『舌の先まで出かかった名前』、青土社、1993=1998、p.62)。 ●「言葉は権力である。手垢がつくほど使い古されてようやく言葉は中性的であるかのようにみえてくる。しかし所詮権力であることに変わりはない。言葉を使わないままでいることはできるだろうか」(nakan,2013.7.4)。 ●「『コミュニケーション障害』とは、あくまでも、われわれの日常生活、社会生活からみて「何か変だ」、「おかしい」、「普通とは違う」、「普通ではない」、「みんなと同じではない」などと判断される、コミュニケーションの一つのあり方にすぎない。むろん日常生活・社会生活から考えれば、「すぎない」などと簡単に済ますことができず、それゆえ治療とかリハビリテーションというものも存在し得ている。しかし、コミュニケーションという活動・言語活動の多次元性からみれば、障害という言葉など全くのナンセンスであり、『コミュニケーション障害』とはたんに人間のコミュニケーション・言語活動の可能性の範囲にあるものにすぎない」(nakan,2013.7.13)。 ●「言葉にしないと分からない。言葉にするとおしまいである。言葉はこの『分からない』のむこうへと、この『おしまい』のむこうへと向かっていく」(nakan,2013.7.26)。 ●「言葉は人を傷つける。だから傷つけないよう言葉を使おうともする。しかし、傷つけるほうがたいてい勝つ」(nakan,2013.7.26)。 ●「生まれ落ちて言葉を習得するまでの間、言葉に捉われることのない言葉以前の自由な生命体としての自分があったはずですが、言葉の世界に入ることによって、ある意味で、言葉に殺されたといってもいい。常に、こうやって言葉を発するそのたびごとに自分が死に続けているというふうに考えこともできるのではないでしょうか」(藤田博史『人形愛の精神分析』、青土社、2006、p.13-14)。 〜このページの先頭にもどります〜 【さ】 ●「AとB。AやBには固有の価値はない。AとBのあいだに、AとBの差異に価値が生じる。この意味で「AとB」はなくてはならない」(nakan,2013.6.1)。 ●「最後にもっとおいしいもの食べさせてあげられなくてごめんね」(大阪市北区天満の若い母親の最後の言葉。2013.5.27 13:18 ネット配信『産経ニュースwest』より)。 ●「・・・例えば、子供が、男の子であれ女の子であれ、人生のある時期にライオンを当然のように怖いと思うようになることはやはり不思議です。なにしろ、ライオンなど、子供たちみなが同じように出くわすものではありませんから。例えば、身体像に書き込まれた原初的データのような形でそれが引き出されるなどと言うことは難しいでしょう。人は何でもでっち上げますから、こうした考え方をすることだってできるでしょうが、それでも何か割り切れないものが残ります。科学的な説明において残滓として残ったものこそ、常に最も実り豊かな考察を導くものです。とにかく、残滓を避けていては絶対に進歩はありません」(ジャック・ラカン〔ジャック=アラン・ミレール編、小出浩之ほか訳〕、『対象関係』(上)、岩波書店、2006、p.46-47)。 【し】 ●「一般に、私達の日常に於いては、言葉は専ら『代用』の具に供されている。・・・言葉には言葉の・・・代用とは別な、もっと純粋な、絶対的な領域がある筈である。と言って、純粋な言葉とは言うものの、勿論言葉そのものとしては同一で、言葉そのものに二種類あると言うものではなく、・・・畢竟するに、言葉の純粋さというものは、全く一に、言葉を使駆する精神の高低によるものであろう。高い精神から生み出され、選び出され、一つの角度を通して、代用としての言葉以上に高揚せられて表現された場合に、之を純粋な言葉と言うべきものであろう」(坂口安吾「FARCEに就いて」(1932)、『堕落論』、新潮文庫(2000)所収、p.15-16)。 ●「人間は誰でも時に、多かれ少なかれ小説家となり、詩人となる」(nakan,2013.5.4)。 ●「失語症によって、規範への、そして反規範へのヴェクトルが共に生じる」(nakan,2013.5.5)。 ●「規則や規範があるのは、それ以前にすでに奔逸で過剰な戯れ、活動が存在しており、そのためある観点からはその戯れに規制をかけざるを得なくなったからである。言語に規則や規範があるのも同じである。失語症とは、言語を失ったのではなく、言語本来のそうした奔逸で過剰な戯れの現われである」(nakan,2013.8.5)。 ●「フーコーを含め、人はどうしても、結果は、原因の内に含まれていることの展開なので、決して原因を乗り越えることがない、と考えがちである。だが、ときに結果は、原因を超え、原因そのものを否定に導くことがある。結果の原因に対する過剰にこそ、「自由」の究極の根拠がある、とも言えるだろう。この過剰があればこそ、原因の規定から逃れることもできるのだから」(大澤真幸『生権力の思想』、ちくま新書、2013、p.261)。失語症が原因で話せないのだ、と一般的に言われる。しかし「話せない」まま話す、失語症のまま話し続けることで、人は失語症という原因に規定されることなく「話せる」ようになる。失語症者の「自由」はここにある。 ●「『しんけん(真剣)』はなぜ『真剣』なのか?」 (nakan,2013.6.1)。 ●「ものを持続させるための新たな手段が生命ということだろう。そして個というものも、ものを持続させるための一つの手段にすぎない。そうした持続という道の中で、その持続に対して対抗し、かつ殉ずる、一つのあぶくのようなものが個であり、主体ということだろう。シニフィアンの連鎖という持続の中で、言葉と言葉の間、シニフィアンとシニフィアンの間に受動的に生じるあぶくを特に人間の主体という」(nakan,2013.7.12)。 ●「私が皆さんに教えていることは、フロイトが人間の中に主体の重みと軸を発見した、ということです。この主体は、個人の経験の総和としての、さらには個人の発達の方向ですらある個人の組織を越えています。私は主体について可能な一つの定義を示したいと思います。つまり主体とは、経験の全体を被い、 経験に命を吹き込み、意味を与えることになる、象徴の組織化された体系である、と定式化することができます」(ジャックラカン〔ジャック=アラン・ミレール編、小出浩之ほか訳〕、『フロイト理論と精神分析技法における自我』(上)、岩波書店、1978=1998、p.66)。→人間における主体とは、端的に、人間自身ではなく、人間において/の中で働き続ける象徴= 言語活動(langageランガージュ)であるということである。ここから、失語症者がなぜ自らの意思に反して失語症状を露呈してしまうのか、考えることができる(nakan,2013.7.14)。 ●「私が説明しているのは、人間は象徴の働きの中に、象徴的世界の中に組み込まれているかぎりにおいて脱中心化された主体であるということです。つまり、まさにこれと同じ働き、これと同じ世界によって、機械は作られています。最も複雑な機械はパロール〔発話、言葉〕によってのみ作られるのです。パロールは、何よりもまずそれによって人がお互いに承認する、交換の対象です。つまり合言葉を言ったからこそお互いに殴り合わないですんだ、といった具合に。このようにしてパロールの流通が始まり、その流通は、代数的計算を可能にする象徴世界を構築するほどにまで膨れ上がります。機械とは、主体の活動から切り離されているかぎりでの構造です。象徴的世界とはまさに機械の世界です。こうして、この世界において主体の存在を構成しているものは何か、ということが問題になります」(ジャックラカン〔ジャック=アラン・ミレール編、小出浩之ほか訳〕、『フロイト理論と精神分析技法における自我』(上)、岩波書店、1978=1998、p.76-77)。→人間は象徴=言語活動(ランガージュ)に対して、機械と同じ位置にいる、ということがよく分かる。脱中心化された主体とはこの位置のことをいう(nakan,2013.7.14) 【た】 ●「楽しいことは悲しいこと」(Y)。 【な】 ●「なくてぞとは、かかる折にやと見えたり(訳文:〈亡くてぞ人は恋しかりける〉という古歌は、こうした折にこそふさわしいように思われます)」(紫式部〔瀬戸内寂聴 訳〕 『源氏物語』「桐壷」、講談社、11世紀初頭=2001、p.17) 【に】 ●「実をいえば、人間のためにできた空気ではなくて、空気のためにできた人間 なのである」(夏目漱石「思い出す事など」(1910-1911)『硝子戸の中』角川文庫(1998) 所収)。 〜このページの先頭にもどります〜 【は】 ●「がんになったことで、子どもとたくさん話ができました。いまは「がんよ、ありが とう」という気持ちでいっぱいです」(俳優入川保則氏の言葉。2011年12月29日(木)10時00 分インターネット配信『日刊ゲンダイ』より)。 ●「みんながみんな同じように、人生は流れである、ということに一致しているで はないか。それだのにどうして反復などという愚かなイデーに思いふけるのだ ろう」(キルケゴール〔桝田啓三郎訳〕『反復』、岩波文庫、1843=1983、p.96)。 ●「『話す』とは大事なことを話すことである。『聞く』とは大事なことを聞くことであ る」(nakan,2013.7.26.以上から、重度失語症者がなぜ医療者にほとんど何も話さないかが分か る。医療者が大事なことを聞かないからである。そしてジャーゴン失語症者がなぜ医療者の言うこ とをほとんど聞かないかが分かる。医療者が大事なことを話さないからである)。 ●「話すということは、それ自体として、逆説的にも、自らがそれほどうまく話せないという事実を露わにする。つまり、話すという自らの行為において、主体はその固有の欠如に出会うのである。また、臨床実践における知るという営みは、理解や洞察の積み重ねには決して還元されず、そこには無知や曖昧さ、失望やフラストレーションがつねに内在している。そして、これらの躓きの石は、、話存在としての我々の歩みを阻むものでは決してない。むしろ、我々はそこから出発し、穴や欠如を露わにすると同時に、そこに何らかの解決を見出すのである。重要なことは、うまく話すことや体系化された知によって語りが保証されることや、それによって快や安堵がもたらされることではなく、ことばと知に内在する欠如を原動力に、話すという行為に伴う未知の発見や驚き、当惑として体験される「偶然」を患者と治療者が共に歩んでいくことなのである。そして、話すことを通じて、「偶然」が反復され、それを、それらを前にして自らの存在についての問い、すなわち、「運命」についての問いを立てることができたならば、「凡庸な不幸」を後にして、主体にとっての固有の在り方を探求していく実践の入り口に我々は立つことになる」(河野一紀『ことばと知に基づいた臨床実践―ラカン派精神分析の展望』、創元社、2014、p.245)。 ●「話し手とは二つの傾向が相対立する場である。話し手は言葉を話す、つまりある道具の支配者である。と同時に話し手は、言葉によってしゃべらされる、すなわち話しているのは言葉である」(J-J・ルセルクル『言葉の暴力-「よけいなもの」の言語学』、法政大学出版局、1990=2008,p.86)。失語症の人が失語症があっても話そうとする・話すことができるのは、この「話しているのは言葉である」という面のおかげである。ここに臨床への大いなるヒントがある。 【ひ】 ●「いつ死んでもいいから、とにかくめぐみちゃんたちとひと言、話ができてから、 私は死にたいと思っているんです。どのお父さんやお母さんもそうです」(拉致 被害者、横田めぐみさん=拉致当時(13)=の母、早紀江さん(76)の言葉。2012年 9月3日(月) 7時55分 インターネット配信『産経新聞』より)。 ●「人は誰も人生のわずかな一瞬において、永遠に自分を定義されてしまう。そ の瞬間に、人は永遠の自分に出遭います」(J.L.ボルヘス〔野谷文昭訳〕「第一夜 神 曲」、『七つの夜』(1980=2011)、岩波文庫、p.31)。 ●「・・・扇子は「せんす」という呼び方でなければならない根拠は何もない。中に はこれを「うちわ」と呼ぶ人がいても構わないし、アメリカ人は「ファン」と呼び、 フランス人は「エヴァンターユ」という。この四つの表象に共通なところは何もな いし、別に涼しい風を思わせる音感があるわけでもない。結局のところ、名前 というのはその程度の区別がつけばよいという割り切りが、「表象」という名 の、つまりは「契約」である。そういう割り切り方が、1660年代に成立した。それ が、近代の出発点である。「言葉」と「物」を「契約」で無理やりつなぐ。うまく機 能すれば、どんな表象も受け入れて使っていこうということで、汎ヨーロッパ的 に動き出した」(高山宏『近代文化史入門 超英文学講義』、講談社学術文庫、2007、p.54)。 ●「アルファベット順の秩序こそ、「表象」のあり方そのもの。アルファベット順で 構成される世界など実際にはどこにもないが、でもアルファベット順は便利だ」 (高山宏『近代文化史入門 超英文学講義』、講談社学術文庫、2007、p.126)。(確かに大変便利だ が、害を及ぼす時もあることに注意。例えば失語症の治療に、絵カードになった事物の名をどんど ん言わせる方法がある。これはすでに百科全書的な知を求める態勢にいる失語症者にはよいか もしれないが、一般に失語症者には迷惑千万なものである―nakan,2013.7.13)。 【ふ】 ●「自然言語人に近い一部の哲学者、宗教者、芸術家、科学者=可知論者的 超人。超人の中の超人たち=不可知論者。つまり、可知論者たちは自然言語 人同様に生きているのであり、超人中の超人たちは遊んでいるのであります。 可知論者たちは大真面目で生きているのであり、不可知論者たちは笑ってい るのであります。不可知論者たちの真骨頂は『世界』を『可知の部分』と『不可 知の部分』とに二分しないことです」(瀬戸章宏、2012.2.1) ●「不在とは存在のより過激な可能性である」(ジョージ・スタイナー〔伊藤誓訳〕『言葉へ の情熱』、法政大学出版局、1996=2000、p.164)。 ●「不可能性こそは、あらゆる想像的なものの母胎であり、最大にして最後の不 可能性、すなわち死こそは、あらゆるファンタスティックの母胎だったのである」 (澁澤龍彦『澁澤龍彦 西欧文芸批評集成』、河出文庫、2011、p.21)。 【ほ】 ●「翻訳においては、音程を等しくする斉唱と、多彩な音程を同時に響かせる多 様性とが織り成す弁証法が、眼を見張るような形で働いている。ある意味で は、翻訳というものは、どんなものでも、多元性を廃止して、種々異なった世界 像を一致させて、〔数学の術語を使えば〕合同のものたらしめようとする試みで あると言ってよい。しかしまた別の意味では、翻訳とは意味を表わす形態を新 しく作り出し、原語に代る叙述を求め、新しい表現が正当なものであることを立 証しようとするものでもある」(ジョージ・スタイナー〔亀山健吉訳〕『バベルの後に』(上)、法政 大学出版局、1975,1992=1999、p.419)。 ●「翻訳に携わる人の仕事といえば、相反する二つの要素を持っている。すなわ ち、原文を忠実に複製しなくてはならないという衝動と、同時に、然るべき形で 自らの力による創造をも行いたいという気持の昂まりとがそれで、翻訳をする 人はこの両者の間の激しい緊張関係の最中で活動してゆくわけである。つま り、翻訳家は他に比類のない形で言語の進化の歴史そのものを自ら〈体験〉 する、すなわち、言語と世界との間、より正確には〈さまざまな言語〉と〈さまざ まな世界〉との間に見られる、相反する価値観の共存を〈体験〉することにな る。翻訳作品のどれひとつを取ってみても、今述べた関係が創造的な性質、 恐らく、虚構の世界を作り出す性質をもつことが試されていると言ってよい。こ う考えてくればよく分かることであるが、翻訳というものは、決して、言語間の 〈界面〉における特殊な、二次的な活動ではないのである。翻訳とは、融合と 分離を同時に目指す、言語の本性を成している弁証法が、必然的に自らを具 体化して表してくるものなのである」(ジョージ・スタイナー〔亀山健吉訳〕『バベルの後に』 (上)、法政大学出版局、1975,1992=1999、p.419-420)。 【ま】 ●「俗なる人は俗に、小なる人は小に、俗なるまま小なるままの各々の悲願を、 まっとうに生きる姿がなつかしい」(坂口安吾「日本文化私感」(1942)、『堕落論』新潮文庫 (2000)所収、p.62)。 【み】 ●「殉死にはいつどうして極まったともなく、自然に掟が出来ている。どれ程殿様 を大切に思えばと云って、誰でも勝手に殉死が出来るものでは無い。・・・死天 (しで)の山三途の川のお供をするにも是非殿様のお許しを得なくてはならな い。その許もないのに死んでは、それは犬死である。武士は名聞(みょうもん =世間での評判・名声)が大切だから、犬死はしない。敵陣に飛び込んで討死 をするのは立派ではあるが、軍令に背いて抜駆をして死んでは功にはならな い。それが犬死であると同じ事で、お許の無いに殉死しては、これも犬死であ る」(森 鴎外『阿部一族』(大正2年=1913)、新潮文庫(1968)『阿部一族・舞姫』所収、p.125)。 【ゆ】 ●遺言 余ハ少年ノ時ヨリ老死ニ至ルマデ一切秘密無ク交際シタル友ハ賀古鶴 所(かこつるんど)君ナリココニ死ニ臨ンデ賀古君ノ一筆ヲ煩ハス死ハ一切ヲ 打チ切ル重大事件ナリ奈何(いか)ナル官憲威力ト雖此(いえどもこれ)ニ反抗 スル事ヲ得スト信ス余ハ石見人(いわみじん)森林太郎トシテ死セント欲ス・・」 (森鴎外「遺言」(大正11年7月6日=1922)、集英社文庫(1992)、『高瀬舟』所収、p.224)。 【り】 ●「理解は忍耐づよくかちとられ、つねに暫定的である」(ジョージ・スタイナー〔工藤政 司訳〕『真の存在real presences』、法政大学出版局、1989=1995、p.184)。 ●「数学では、物事を理解することはしない。慣れ親しむだけだ。―ジョン・フォ ン・ノイマン」(イアン・スチュアート〔水谷淳訳〕「数学者の数学に関するつぶやき」『数学の魔法 の宝箱』、ソフトバンク・クリエイティブ(2009=2010)、p.98。これは決して数学に限らない)。 |
| 〜このページの先頭に戻ります〜 |